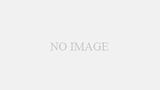鏡開きの乾杯の流れは?
主に、お祝いの行事で行われる鏡開きなので、 基本的には明るく元気良くが鉄則です。 明るく元気よく 「よいしょ! よいしょ! よいしょ!」と 掛け声をするのが一般的なようです。 他には「せーの!よいしょ!」のかけ声で 酒樽の蓋を割る場合もあります。鏡開きには、事前の準備が必要!
スムーズに割る為に事前の準備が必要です。 酒樽を購入して鏡開きをする場合は、木槌やバールなどの工具であらかじめ鏡(酒樽の蓋)を開けておく必要があります。 または、酒樽と清酒を分けて購入し、酒樽に清酒を入れた後で、蓋をするという方法もあります。 この場合は、元から蓋が外れた状態で購入するため、工具を使って蓋を開けるという作業をする必要がなくなります。 予め、鏡を外しておき、酒樽に再び蓋を揃えて乗せておくことで、お祝いの日の大切な衣装にお酒が飛び散るのを防ぐこともできます。 それに、何より割れやすくなります。 「あれ?割れないな…」と焦らずにスムーズに進行することができるというわけです。 蓋の開いていない酒樽を購入して蓋を開ける場合は、開ける作業をするときに、木屑などのゴミが入りやすいので、 作業後に網などでゴミをすくってきれいにするようにしましょう。 こういった手間などから、酒樽と清酒を分けて購入して準備する人が増えているようです。鏡開きの意味は?
鏡開きは鏡餅で行う時と お酒でする時がありますね。 鏡開きはもともと武家の時代に始まったとされている行事です。 お正月の間に年神様の依り代や神様の分身として飾られていた鏡餅を食べることで家族の一年間の無病息災を願う行事です。 酒樽で行う鏡開きはお正月にすることもありますが、それ以外にも結婚式などのお祝いの席で行われます。
樽を開くことで
これからの運を開くという意味があります。
日本酒はお米から作られる神聖な物とされていて、神様にお供えしたりすることからお祝いの席にはかかせないものとされていました。
このお酒を酌み交わすことで願い事の成就を祈るとされています。
鏡餅も酒樽のフタも、共通することは丸い形をしているということ。
昔、日本では丸い形をしているものを鏡と読んでいたとされています。
『丸いもの=鏡』を割ることを鏡開きと呼ぶようになりました。
厳密にいうと開くというより切ったり割ったりしていますが、武家の時代に始まった鏡開き。
切るや割ると言った表現は切腹など縁起が悪いものを連想させるために縁起のよい“鏡開き”という表現をされるようになりました。
どちらの鏡開きの意味も覚えておきたいですね。
酒樽で行う鏡開きはお正月にすることもありますが、それ以外にも結婚式などのお祝いの席で行われます。
樽を開くことで
これからの運を開くという意味があります。
日本酒はお米から作られる神聖な物とされていて、神様にお供えしたりすることからお祝いの席にはかかせないものとされていました。
このお酒を酌み交わすことで願い事の成就を祈るとされています。
鏡餅も酒樽のフタも、共通することは丸い形をしているということ。
昔、日本では丸い形をしているものを鏡と読んでいたとされています。
『丸いもの=鏡』を割ることを鏡開きと呼ぶようになりました。
厳密にいうと開くというより切ったり割ったりしていますが、武家の時代に始まった鏡開き。
切るや割ると言った表現は切腹など縁起が悪いものを連想させるために縁起のよい“鏡開き”という表現をされるようになりました。
どちらの鏡開きの意味も覚えておきたいですね。
まとめ
お祝い事の席で鏡開きをやっている場面は目にしたことがあっても、意味までは知らない方が多かったのではないでしょうか。 お餅でやる場合と酒樽でやる場合とで多少意味が違います。 でも、丸いものを鏡と呼んでいることや神様が宿るありがたいものという部分では重なるところもあります。 せっかくのお祝いの行事なので正しい意味と流れを知って、思い切りお祝いするようにしたいですね。スポンサーリンク

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/172fa621.5bb1ed8b.172fa622.8c7da701/?me_id=1201553&item_id=10000024&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-saketen%2Fcabinet%2Fminitaru%2F046.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-saketen%2Fcabinet%2Fminitaru%2F046.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)